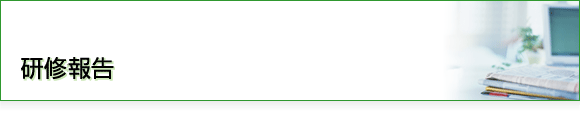H24年12月8日(土) 「看護者のための認知行動療法研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ2F 参加者 140名 内容 講義 「認知行動療法の基本」
「認知行動療法の実際」講師 医療法人北仁会 旭山病院
臨床心理室課長 大宮 秀淑先生 -
アンケート結果において「研修内容」「今後に役立つか」「満足度」のすべてにおいて、90%以上の高い評価を得る結果となりました。「大変わかりやすくおもしろい」「自身の看護を振り返る良い機会」「事例でイメージがわいた」など受講者の声が聞かれています。受講後の即実践を形作るためには、学習の機会を多く体験していく必要があると感じていますが、この受講で学びが深まったことと考えます。今回、募集人数を大きく超える参加希望がありました。興味・関心のある内容であり、今後の看護に役立てて欲しいと考えています。
H24年11月17日(土) 「認知症看護研修会」
-
会場 函館渡辺病院西棟5階ホール 参加者 66名 内容 講義 「認知症の理解」
「認知症看護の実際」講師 財団法人仁明会 仁明会病院
看護師長 南 敦司 先生 - 認知症の理解・看護の実際について、講義の内容が「わかりやすかった」また今後の活動や職場において「役立つ」とされ、80%以上の受講者に高い評価を受けました。研修への期待度や研修を終えた満足度もほぼ全受講者で高い評価となっています。今回の受講で認知症看護に興味を持ち、また、理解を深めることができたとの声が聞かれています。笑顔で対応することの大切さを再認識し、実践していくことの重要性を確認できた研修会でした。受講者にとっては自己の向上が図れたことと感じています。
H24年10月27日(土) 「精神科初心者研修会」
-
会場 滝川文化センター 参加者 55名 内容 講義 「精神看護の基本」
「疾患理解と対応ポイント」講師 特定医療法人北仁会 旭山病院
看護副部長 齋藤 香奈恵 先生 -
「精神看護の基本」「疾患理解とポイント」といった講義内容について、分かりやすい・役立つといったアンケート評価を受けています。また、研修への期待度があまり高くなかったものの、研修を終えて「満足した」と回答された参加者が多く、高い評価であったと考えています。
今後も、新人を対象とした研修会を継続開催していくことは必要であると考えています。次年度はより専門的な内容を含めていくよう検討しています。
H24年10月13日(土) 「行動制限最小化看護研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 129名 内容 講義 「行動制限最小化の基本的な理解と動向」
「拘束帯の使用方法と拘束時の二次障害」
「行動制限最小化への取り組みの実際と課題」講師 (医)昨雲会 飯塚病院 行動制限最小化看護
精神科認定看護師 湯田 文彦 先生 -
参加者は129名と関心度の高い研修会となりました。午前の講義では基本理解と動向、午後の講義では拘束帯のデモンストレーションを行ないましたが、事故事例の話も実際に目で見て確認することができ、参加者にとっては大変参考になった場面であったと感じます。講義内容ではおおむね理解度の評価が高く、実践でも役立つ結果になりました。また「行動制限について」を改めて考える良い機会につながったことと感じています。
今回、意見・要望に、研修時間に単一業者が入っていたことへの不満が寄せられました。今後、業者等が入り研修内容に関わることがある場合、その内容が事前にわかるような発信方法やオリエンテーションでの説明等、必要な処置を考えて検討していきたいと考えています。
H24年10月4・5日 「東北学術集会及び北海道看護研究発表会」
-
会場 札幌コンベンションセンター 参加者 233名 内容 講義 「これからの精神看護」 講師 聖路加看護大学 精神看護学科
教授 萱間 真美 先生 -
「これからの精神科看護」のアンケートにおいて、内容については「分かりやすかった」、今後役立つかについては「役立つ」と言う評価になり、高評価である結果になりました。また、看護研究発表について「どちらかと言えば」を含むと、ほとんどの方が「学べた」「わかりやすかった」「役立つ」と回答されて、こちらも高い評価となりました。「研究発表が参考になるものが多かった」「モチベーションが向上できた」「精神科看護師であることに自信が持てた」などの声が感想がありました。
ほかに「抄録を早く受け取りたい」等の意見が複数ありました。どのような研修会であっても、事務局においては最善を尽くし、ご要望に近づく姿勢で準備していることをご了承いただけると幸いと感じています。
H24年9月15日(土) 「リーダーシップ研修」
-
会場 札幌ホテルノースシティ2F 参加者 47名 内容 講義 「看護に求められるリーダーシップとは」
「リーダーシップの実際」
講師 東海大学健康科学部看護学科
准教授 天賀谷 隆 先生 -
アンケートの結果では「分かりやすい」「役立つ」と言った意見が多く聞かれましたが、「どちらかと言えばわかりにくかった」という意見も少数ありました。全体的には講義の内容や研修の満足度は高く、具体的な例を出して話されていたため、大変わかりやすく楽しい研修会であったとの意見が多く聞かれています。「興味深い理論の内容を聴くことが出来た」「今後の活動に生かせるように努力したい」「自身の振り返りにつながった」「どのようにスタッフに伝えたら良いか大変勉強になった」などの現場の声が聞かれています。リーダーシップ研修への期待度は高く、次年度も継続して行なう方向で検討していきたいと考えています。
H24年9月1日(土) 「発達障害を学ぶ研修会」
-
会場 帯広市生涯学習部とかちプラザ401号室 参加者 65名 内容 講義 「成人の発達段階の理解と関わりのポイント」
講師 道立緑ヶ丘病院
精神科医長 長沼 睦雄 先生 -
講義を受けての知識・技術において「どちらかと言えば学べた」と評価されていますが、内容について「どちらかといえばわかりにくかった」という結果が出ています。また、研修会への高い満足度は得られない評価となりました。しかし、意見・感想の中には「学びたい内容だった」「概論だけではなく看護へのアプローチ方法が聞けてよかった」「期待していた研修内容だったのでスタッフに伝えていきたい」との声が聞かれています。
今回の研修では開始時間の遅れがあり、参加者へのご迷惑になったことをお詫びとし、同様のことが起こらないよう、今後の研修会に向けて十分配慮していきます。
H24年8月4日(土) 「訪問看護研修会」
-
会場 網走女性センター 参加者 28名 内容 講義 「精神科訪問看護の基本と実際」
講師 訪問看護ステーション「やまのて」
副部長 谷藤 伸恵 先生 -
研修内容に関しては満足度が非常に高く、事例を挙げての関わりについて「分かりやすかった」という意見が多くありました。具体的な関わりや支援方法が、参加者にとって学びとなった声が聞かれています。今回、会場がわかりにくく探したと言う意見も多く頂いているため、今後、開催場所に応じて地図等を考慮していく必要を感じました。また、今年度は函館・網走と地方での訪問看護研修会であったため、来年度は札幌での開催を検討しています。
H24年7月28日(土) 「師長研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 2F 参加者 42名 内容 講義 「師長が行う看護管理の基本と実際」
「管理者に求められるコミュニケーション技術」講師 特例社団法人 日本精神科看護技術協会
副部長 龍野 浩寿 先生 -
午前、午後ともに講義形式で展開され、管理の現場で活用できる内容でした。アンケートから「講義内容」と「今後に役立つか」の結果は、ほぼ全員が分かりやすく、役立つと回答されました。研修前の期待度は19名が「期待していた」に対し、研修後の満足度に関しては32名が「満足した」と回答され「どちらかといえば満足した」を含めると38名が満足できた研修内容でした。また、精神科看護管理の実際に関して、具体的な事例を使い人材育成などを考える研修スタイルも必要と感じ、次年度に向けて師長研修の継続を考えています。
H24年7月21日(土) 「服薬コンコーダンススキルを学ぶ研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 75名 内容 講義 「コンコーダンスの概念理解」
「コンコーダンススキルの実際」講師 医療法人智徳会 岩手晴和病院
これからの暮らし支援部
副部長 安保 寛明 先生 -
研修は、概念とスキルの内容の分かりやすさ、活用度・満足度ともに高い評価でした。しかし、今回の研修会の期待度が低かったことを含めて、コンコーダンス・スキルへの理解が十分広まっていない要因が考えられました。また、研修会名だけでは内容が伝わりづらかったということを踏まえ、題名の工夫を今後の研修会検討に含めていきたいと考えます。これからも研修会における薬に関する介入は必要性が高いと感じていますが、この研修会を通し動機付けにつながったものと考えています。
コンコーダンス・スキルの概念が、これから多くの人に認知されていくことと、今回の参加者各自がさらなる学習意欲をもって学びを深めていただければ幸いです。
H24年7月7日(土) 「服薬心理教育を学ぶ研修会」
-
会場 旭川トーヨーホテル 参加者 37名(内、学生6名) 内容 講義 「地域生活を支える薬物療法」 講師 (医)宙麦会 ひだクリニック
院長 肥田 裕久 先生講義 「服薬心理教育の実際」 講師 (医)宙麦会 ひだクリニック
副院長 木村 尚美 先生 -
講義に関しては分かりやすい、役立つと言った結果でした。患者さんの薬に対する感じ方や患者に寄り添う薬物療法を判りやすく説明され、より実践的な内容であったという評価を受けています。今回の研修会、同様の内容について深く学んでみたいという意見もあり、講義を受けた参加者各自が意欲的に学習意欲を持てたということは、今後のスキルアップにもつながる大きな意義のある研修会であったと感じています。また、研修の学びを現場の関わりに生かすことが出来る人材が多く育成されることは、我々にとっても喜ばしいことです。薬物療法に関連した研修会は今後も継続していきながら、開催地を随時検討していく考えです。
H24年6月30日(土) 「主任研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 2F 参加者 AM 56名
PM 48名内容 講義 「主任が行う看護管理の基本と実際」
「管理者に求められるコミュニケーション技術」講師 北海道大学病院 看護部
キャリア支援室師長 中西 千代美 先生 -
内容については、午前と午後の講義共に「分かりやすかった」「どちらかといえば分かりやすかった」と高評価でしたが、「どちらかといえば分かりにくかった」と10%の参加者が評価される結果となりました。午後の講義で急遽グループワークを設定されましたが、「同じ悩みを共有できた」「他の施設の主任と話す機会が勉強になった」という意見も寄せられ、「がんばろう」と次につなげていく前向きな姿勢がうかがえます。また、「もう少し具体的な内容を」「じっくり聞きたい」という声も寄せられていますが、大変参考になった・現場に活用できると言う結果となっています。
次年度も管理者研修として継続を予定していますが、随時内容について検討していきたいと考えています。
H24年6月16日(土) 「依存症を理解する研修会」
-
会場 札幌市民ホール2階会議室 参加者 107名 内容 講義 「依存症の理解と治療」 講師 医療法人北仁会 旭山病院
院長 山家 研司 先生講義 「依存症看護の実際」 講師 成増厚生病院付属 東京アルコール医療センター
看護師長 韮沢 博一 先生 -
アンケート回収率も高く、結果も「依存症の理解と治療」「依存症看護の実際」ともに高い評価を得ています。「どちらかと言えば」を含めるとほぼ100%が「わかりやすい」「役立つ」に達する結果となりました。
研修参加者からは、回復した当事者の体験談を聞けたということで印象に残ったり、実体験と重ねたりすることで理解を深めることができたという意見・感想が多く出ています。講義についても「聞きやすかった」という意見や、依存症理解からケアにつなげていく上で今後の参考になった意見があげられました。今回の研修を継続的に行って欲しい等、関心の高さも伺えた結果となり、今後も企画継続の必要性を感じています。
H24年6月9日(土) 「訪問看護研修会」
-
会場 社会医療法人 函館渡辺病院 5階 参加者 47名 内容 講義 「精神科訪問看護の基本的技術とアセスメント」
「ケース検討会」
講師 聖路加看護大学 精神科看護学
教授 萱間 真美 先生 - アンケート結果では、わかりやすさ・期待度・活用度ともに評価が高いものになりました。参加者にとっても「課題が見えた」「参考になった」「勉強が必要と感じた」「やりがい・望みがもてた」など看護のあり方への再認識やこれからの看護への動機につながる研修でした。
今後は、研修内容についてを継続していく方向で、開催地については随時検討していきたいと考えています。
H24年5月19日(土) 「退院支援研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 102名 内容 講義 『退院支援に求められるもの』 講師 (特社)日本精神科看護技術協会
専務理事 仲野 栄 先生シンポジウムテーマ 『退院支援の実際』 -
講演内容について「分かりやすい」「役立つ」と回答された方が多く、高い評価になっています。参加者からは自己の振り返りになった、多職種連携の理解が深まったという感想がある中、具体的な支援方法を知りたかったという退院支援への関心の高さが伺えました。精神科医療や福祉等の法制度の変化や診療報酬改定の面からも、退院支援と地域生活支援は強く求められています。患者や家族を支えていくために、これらの支援の方法や質を高めていくことが必要であるとともに、医療従事者に対する学びの機会を提供していくことが課題の一つ言えるでしょう。次年度、研修企画の継続を検討していきたいと考えています。
H24年4月21日(土) 「看護研究研修会」
-
会場 札幌ホテルノースシティ 参加者 66名 内容 講義 「精神科臨床ですすめる看護研究」
― 看護研究の意義と目的 ―
―研究のプロセスとまとめ方―講師 札幌医科大学保健医療学部看護学科
准教授 澤田 いずみ 先生 - アンケートでは「学べた」「分かりやすかった」「役立つ」と言った意見が大半でした。参加者にとって、講義は聞きやすく丁寧であったという印象もあり、満足度の高い研修会であった様子です。「どこから手をつけようかと思っていましたが、なんだかできそうな気がしてきました。」などといった感想からも、これから看護研究に取組む方にとっては進め方や困ったときのヒントが得られた研修会であったと考えています。また、もう少し時間をかけて学びたかったという意見もあり、基礎から応用といった方向で研修時間を増やしていくことも視野に入れ、来年度の開催に向け検討していきたいと考えています。